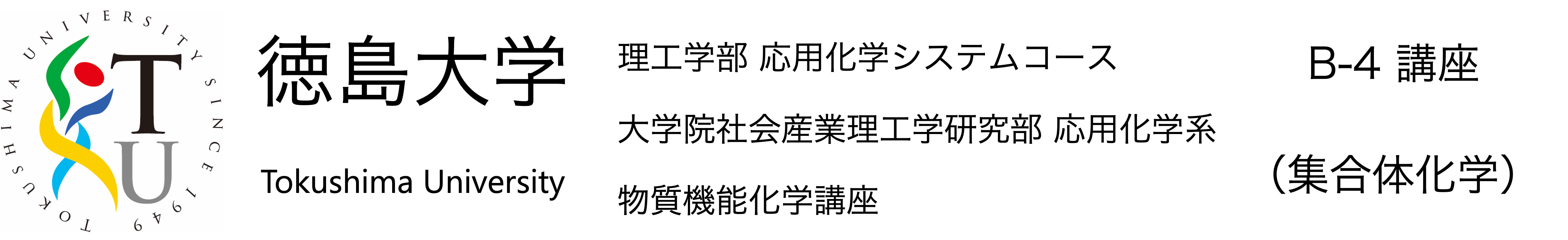研究内容
B-4講座では、以下のテーマに関して研究を行っています。詳細は各グループのページをご覧ください
結晶成長の研究(担当教員:鈴木)
結晶成長とは、無秩序に運動している環境相中の分子が突如として規則的な構造を形成する、ドラマティックな相転移現象の一つです。できた結晶を使うことで、その中の分子の立体構造をきわめて精密に解析できたり(DNA、タンパク質の分子構造)、これまでになかった特性を持つ新材料を作りだす(発光ダイオード、半導体基板)ことも可能です。そのため、いくつかの歴史上大変重要なノーベル賞は、結晶成長の成功なしには語れないものが多いです。しかし、そのようなときには結晶成長自体が大変難しいことが多いですが、それは、実はまだ結晶成長には解き明かされていない謎が多く存在することによります。その謎に、「その場観察」の手法で切り込んでいるのが我々のグループです。是非皆さんの力を貸してください。そして、一緒に新しい世界を切り開いていきましょう!
NMRや分子シミュレーションによる溶液化学の研究(担当教員:吉田)
溶液化学グループでは、主に高温高圧の水および水溶液の構造・ダイナミクス・反応を対象に、NMR分光法と分子シミュレーションを組み合わせながら、物理化学の視点からの研究を行っています。具体的には、動的NMR法による水や水溶液中の並進・回転といった分子運動の観測や、実験のみからは知り得ない詳細な情報を得るために、実験的に得られた情報と突き合わせながら分子動力学計算を用いることで、溶媒和と並進・回転・振動などのダイナミクスがどのような関係性にあるのかの解析を行っています。さらには、高温高圧条件の水・水溶液の応用展開として、環境調和型反応のNMR解析を行い、無触媒条件下での糖類の高付加価値有用物質への転換法の開発などに取り組んでいます。
機能性ナノ材料の開発(担当教員:倉科)
原子レベルまで薄くした二次元シート状化合物は特異な物性を示します。ここでは遷移金属の層状化合物を1層ずつに剥離することでナノシートを合成し、その酸化還元に基づく特性を研究しています。銅水酸化物ナノシートを用いた電極ではグルコースの電解酸化が可能であることを見出していており、これらの特性を生かした新たな電気化学的デバイスの作成を目指して研究しています。また排水中にある物質回収による水の浄化についても研究しています。環境中に流出すれば有害ですが回収できれば資源となる物質は多く、さらに環境に負荷の少ない物質を使った回収を目指して研究をしています。ここではキトサン(カニ等の殻由来の高分子)を原料にして、ホウ酸を吸着する素材を開発しています。